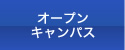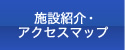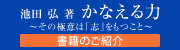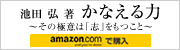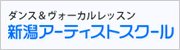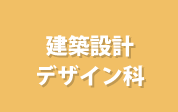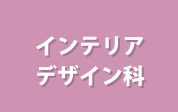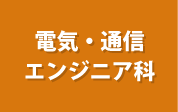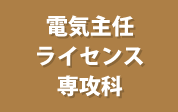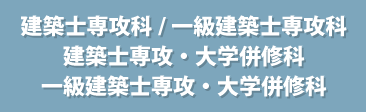◆NIT ブログ
【お仕事紹介】測量・土木・電気にはどんな仕事がある?
こんにちは! 前回のブログで、建築分野の職業について知りたい!という方向けに、お仕事の紹介をしました。☞ブログ記事はこちら 今回は測量・土木・電気のお仕事紹介をしていきたいと思います🌝 【測量士】 橋やトンネ [...]
【お仕事紹介】建築にはどんな仕事がある?
こんにちは! 高校生の皆さんは進路研究を始めた方も多いかと思います。 いろいろな職業を調べるにあたり、「建築やものづくりに興味があるけどどんな仕事があるんだろう・・?」と 気になった方に、今回は建築のお仕事紹介をして [...]
【新設学科紹介】電気主任ライセンス専攻科
----------------------------------------------------------------------------------------------- 2024年度生募集よ [...]
【新設学科紹介】ドローンソリューション専攻科
----------------------------------------------------------------------------------------------- 2024年度生募集よ [...]
電気工事士とは?資格の種類や取得方法、合格難易度まで【なり方】を詳しく解説!
===================================== 電気工事士とは?資格の種類や取得方法、合格難易度まで【なり方】を詳しく解説! 電気工事士の仕事に興味を持っているあなた。 電気工 [...]
建築デザイナーとは?仕事内容、なり方や関連資格、デザインのトレンドまで
===================================== 建築デザイナーとは?仕事内容、なり方や関連資格、デザインのトレンドまで 建築物の外観、空間をデザインする職業。建築デザイナーになるには、 [...]
大工になるには?資格の種類や仕事内容、スキルアップに必要なことは【卒業生インタビュー付】
===================================== 大工になるには?資格の種類や仕事内容、スキルアップに必要なことは?【卒業生インタビュー付】 大工の仕事は、建物の骨組となる柱や梁、天井、 [...]
インテリアデザイナー、インテリアコーディネーターになるには?必要資格と難易度、取得方法、学校選びのポイントなど
===================================== インテリアデザイナ-やインテリアコーディネーターになるには?必要資格と難易度、取得方法、学校選びのポイントなど インテリアデザイナーとは [...]
【建築・インテリア・大工・土木測量・電気】NIT卒業生インタビュー【お仕事が分かる!】
===================================== 【NIT卒業生インタビュー特集!】 NITは、この2021年3月までに6400名以上の卒業生を輩出しています!卒業生は、ほとんどの方が専 [...]
【建築設備システム科】 ~就職内定者インタビュー~
----------------------------------------- 建築設備システム科の内定者インタビュー! 出身高校 中越高校出身 内定先 一般住宅、公共施設、店舗、マンション、あ [...]
【電気電子工学科】 ~就職内定者インタビュー~
――――――――――――――――――――― 電気電子工学科の、内定者インタビューをお届けします 出身高校 新潟東高校出身 内定先 高速道路でお馴染みのネクスコ東日本のグループ会社で、 高速道路の [...]
【環境測量科】活躍している卒業生を取材に行きました!
―――――――――― NITではときどき、活躍している卒業生の様子を取材に行っています 今回は環境測量科を平成25年に卒業した南波さん(新潟県 県央工業高校出身)のところにお邪魔しました 南波さんは、卒業してからずっ [...]