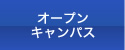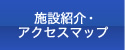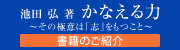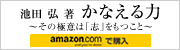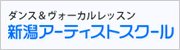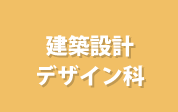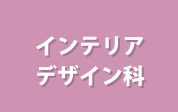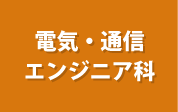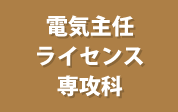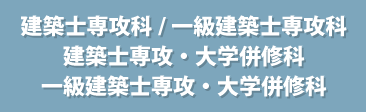◆NIT ブログ
電気工事士とは?資格の種類や取得方法、合格難易度まで【なり方】を詳しく解説!
=====================================
電気工事士とは?資格の種類や取得方法、合格難易度まで【なり方】を詳しく解説!
電気工事士の仕事に興味を持っているあなた。 電気工事士は将来的にも需要が安定しており、 「手に職を付けたい」とお考えの方にピッタリの職業です。ここでは、電気工事士の具体的な仕事内容、やりがいや大変さなど皆さんが気になる点について卒業生の実体験エピソードも含めながら、ピックアップしてまとめていきます。
電気工事士とは
電気工事士は、わたしたちの生活に無くてはならない「電気」を支えています。
住宅やビル、マンション、工場、スーパーなどの様々な建物で、電気が安全に使用できるように工事や管理をしたり、 携帯電話やインターネットが繋がるように基地局をつくったり、電車が毎日安全に運行できるように鉄道の電気設備を管理したり。ときには、地震や台風などの災害が起きたとき、いち早く現場に駆け付け、電気設備を復旧させてくれているのも電気工事士です。日本のエネルギー源である電気を扱える電気工事士は職業としての価値も高く、 社会からの需要がなくならない安定した職業だと言えるでしょう。
電気工事士の資格の中で最も有名なのが、「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」の2つです。資格によってできる仕事の範囲が異なるのですが、例えば二種を持っていると「一般用電気工作物の電気工事の作業」ができます。これは簡単に説明すると、「住宅やコンビニなどの小規模のお店の電気工事ができるようになりますよ」ということです。電気工事士は資格を取得し、免状を交付されていないと実務工事は出来ません。
無資格でもできる業務内容としては、手元作業と呼ばれる先輩の補助作業が中心で、 その他、荷物運びや現場の掃除などの単純作業のみになります。
電気工事士の資格を持っていなくても電気の仕事に携わることはできますが、 担当できる業務範囲は限られてしまうので、将来的には資格を取ることを視野に入れておいたほうが良いでしょう。
======================================================
<電気分野に興味があるのなら… まずは新潟工科専門学校に資料請求&LINEお友達登録!>
======================================================
電気工事士資格の種類・取得方法・合格難易度など
電気工事士の資格には、「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」の2種類があります。 第二種が電気工事士の入門編となっており、 第一種がより上位の資格です。そのため、基本的には第二種電気工事士の受験から始める方が多いです。ここでは一種と二種の違いや試験概要などについてまとめています。
電気工事士「一種」と「二種」の違い
電気工事士として活躍したいのであれば、まずは第二種電気工事士、更に経験を積んで第一種電気工事士と、どんどん上位の資格取得を目指していきましょう。第一種電気工事士の資格まで取得することによって、携わることのできる工事の幅が広がるのはもちろん、転職をする際にもとても有利です。
「第一種電気工事士」試験概要まとめ
「第二種電気工事士」試験概要まとめ
電気工事関連の資格アレコレ
電気工事士関連の資格は、まだまだたくさんあります。必要な仕事に応じて、できるだけたくさんの資格取得を目指しましょう。
一例として、下記のような国家資格があると就職・転職に有利でしょう。
このように、たくさんの国家資格があります。自力で取得するのは難しい資格ですが、専門学校では上記のような資格取得を目指すカリキュラムが整っています。
電気工事士の仕事内容、やりがいとは
電気工事士に興味を持つと、工事現場のリアルな様子や、仕事で大変なことなどが、気になりますよね。ここでは実際に、電気工事士の仕事で大変なこと・やりがいをお伝えしていきます。
お仕事の具体例・就職先選択肢の広さ
電気工事士の1日の流れは、勤め先の会社や担当する仕事内容によって異なります。日勤で働く方の例をまとめてみました。
<日勤(8:00~17:00)の場合>
7:00 事務所に集合し、荷物を積んで現場へ出発
▼
8:00 到着後、1日の作業内容を確認し、業務開始
▼
◎新築住宅の建設にともなう電気工事
図面を見ながら決められた場所に配線工事を行ったり、コンセントや照明器具の設置工事を行ったりします。
▼
12:00 お昼休憩
▼
13:00 午後の作業を開始
午前中に行った工事の続きや、テレビアンテナやエアコンなどの取り付け。1日の作業内容が一通り終わったら事務所へ戻ります。
▼
17:00 事務所へ戻ったら、作業日報の記入と次の日の準備を行って解散
電気工事士は携わる仕事内容によって夜間作業を行う場合もあります。 特に鉄道の電気工事等は、電車の運行が終了した後にしかできない作業もあるので夜間作業が発生しやすいです。
電気工事の仕事は、思った以上に沢山の仕事の種類があります。大きく分けると建築電気工事と鉄道電気工事の2種類に分かれます。
どんな点がやりがい?逆に大変なことって?
電気工事と聞くと「大変そう・難しそう」というイメージを持つ方も多いと思いますが、 電気工事業界で活躍している方の中には、10年・20年と何年も長く続けている方が多くいます。配線を間違えないよう慎重な作業が必要な職業ではありますが、 それだけ長く続けられる理由は、電気工事士ならではのやりがいや魅力があるからに他なりません。下に電気工事士のやりがいについてまとめてみました。
1.達成感(安堵感・充実感など)
達成感はこの仕事で1番と言っていいほどの、やりがい・魅力であると言えるでしょう。 苦労を乗り越え、試行錯誤した現場に電気がついた瞬間、「良かった。苦労した甲斐があった。」「自分がこの電気をつけたのか。」と様々な思いを感じるそうです。
2.成長を実感しやすい
資格を取得した時、できる工事が増えた時、周りから「良い仕事をするようになったな。」と言われた時、 1人で現場をおさめられるようになった時など、様々な瞬間で成長を実感でき、そこにやりがいがあるとのことでした。
3.技術・実力を評価してもらえる
現場で必要なのは、工事を正確に素早く進める技術や知識です。 逆にいうと、技術が身につけば、工事現場で任されることも増えて、存在感が増していきます。 その頃には、会社からの評価も高まり、昇給など目に見える形でかえってくるものがあります。
4.社会貢献度の高さ・感謝される喜び
電気は様々な場で必要とされています。社会に貢献できているという喜びはこの仕事ならではだ、という声も多くありました。 お客様から「ありがとう。これで便利になった」「本当困っていたから、助かったよ。」と声をかけてもらえた時も、嬉しい瞬間の1つとのことでした。
★NIT卒業生にも仕事のやりがいについて聞いてみました!
「電気工事は自分で配線を組んで、照明器具を取り付け、点灯試験までの一連の流れを自分で行います。最後点灯試験をして電気がついた時には達成感とやりがいを感じます」(2013年 電気電子工学科卒 小林さん)
将来性はどう?需要が高まる理由
電気業界は日常生活に関わる職種であるため、需要がなくなることはありません。便利な世の中になるほど、それを支える「電気工事」の件数は増えます。ただ、「仕事はあるのに、工事できる人がいないから会社を継続していけない・・・」という事例が多くあるのです。
これから先も、都市再開発が活発化し、工場・オフィスビル・大規模マンション・アミューズメントパーク・複合施設の建設が進んでいきます。
しかし、これらの工事は高電圧の電気工事となるため、第一種電気工事士が必要となります。この資格は、免状の取得には「第二種電気工事士を取得後5年以上の実務経験を有する」となっていることもあり、「電気工事の仕事の経験者」が合格後の免状を取得できます。免状の取得に制限があるために技術者の急激な増加には繋がらず、充足するに至らないのが現状となっています。ですので、電気工事士をある程度抱えなければ、電気工事会社自体が生き残れない世の中になっていくと予想されます。
ハローワークの有効求人倍率から見ても電気業界は他業界に比べ採用活動が活発化しています。今電気業界は1人の求職者に対して4.57件の求人案件があり、これまでに見ない売り手市場になったと言えます。また、電気工事士の試験受験者は、年々増えています。 2006年から2016年にかけて、第二種電気工事士の筆記試験・受験者は、約1.7倍になっています。 電気業界は大手企業が人員募集を多くかけている業界のため、大手企業に就職できる可能性も高く、不景気の今 電気業界の人気が高まりつつあります。
独学でも大学でもない「専門学校」で電気工事士を目指すメリットとは
高校や大学・専門学校などの電気を扱う電気科や工学科に通えば、 基礎や専門知識を学ぶ方法もあります。 特に、専門学校では授業のカリキュラムに電気工事士の資格取得が組み込まれていることもあるので、 在学中に資格を取得して就職に活せる学校も多いようです。この、「試験対策授業を受けられる」というところが進学の大きなメリットになります。
一方、大学の工学部ではそもそも電気工事の対策授業を行っているところがほとんどないため、独学での受験となります。そのため、電気工事士を目指して大学に進学することを考えていた方は、一度立ち止まって考えてみる必要があります。
その他、職業訓練校や通信講座を利用して電気工事を学び、 資格を取得している方もいます。独学の場合、かかる費用は通信講座や講習会よりも安くはなります。が、電気工事士には筆記以外に技能試験があります。その対策を別に考えなければいけません。既に見習いとして働きながら電気工事士の資格取得を目指す人は、職場で先輩の実務を見ながら技能の勉強をすることができます。ただ、まだ働いてもいない状態の場合、技能試験の対策を独学のみで学ぶのは非常に難しいです。独学で進めていこうと思っても、練習で完成した配線が合格に値するものなのかどうかをテキスト頼り判断することは難しく、挫折してしまう人も少なくありません。特に初心者の人で「第二種電気工事士」の資格から取得しようと思っている人は、知識が全く無い状態からのスタートなので、なおさら独学での勉強は難しいでしょう。
電気工事士を目指したいと考えている方は、まずは「専門学校への進学」を考えてみてはいかがでしょうか。
実際に新潟工科専門学校にて授業を受けた感想について、卒業生に聞いてみました。
小林 良和さん(十日町高校出身/電子電気工学科2013年3月新潟工科専門学校卒業)
NITでは資格取得や就職活動で先生方の強いサポートを受けられます。在学中に取れる資格もたくさんありおすすめです。他にも、NITにはプロが来て電柱を昇る訓練をする授業があり、この授業が現場に行ってから非常に役に立ちました。本当にプロの方が教えてくれるので「実際にこうした方がいいよ」とか「そうすると危ないよ」という危険なポイントも教えてくださるのでとても役に立ちました。
======================================================
<電気分野に興味があるのなら… まずは新潟工科専門学校に資料請求&LINEお友達登録!>
======================================================
何も決まっていなくても大丈夫!1・2年生も大歓迎♪
体験実習もたくさんあり、進路活動に役立つ情報が詰まった一日です!
ご参加お待ちしています! ▶詳細はこちら